『種の起源』 ダーウィンの進化論
指折りの科学者
チャールズ・ダーウィン
彼の学生生活やビーグル号の旅を
たどりながらダーウィンの
進化論の神秘を説く
(長文です)

地球 ...
数知れないほどの生命が生まれ
子孫を残しては死んでいく
そうして生命はこの星を覆いつくした
学校ぎらいのチャールズ・ダーウィンが
船酔いしながら世界中を探検し
生物学の大問題を解明した
それを本にしたのが「種の起源」である
世間の批判に耐えながら出版した
この科学の名著は生物学に革命をもたらし
人間の世界観を変えてしまう
ビーグル号で旅に出たダーウィンは
どのようにして進化論に至ったのか

Charles Robert Dawin 1809-1882
チャールズ・ロバート・ダーウィン
イギリスの自然科学者。卓越した地質学者・生物学者で、種の形成理論を構築。エディンバラ大学、ケンブリッジ大学。主な業績に「種の起源」「ビーグル号航海記」「自然選択説」など。73歳没。(チャールズ・ダーウィン Wikipedia)
「種の起源」1859年11月24日初版刊行
学生時代
" Wisdom begins in wonder " Socrates
「知恵は、『なぜ?』から始まる。」
ソクラテス
宗教に束縛されない首都エジンバラ
西暦1825年、近代化の中心のひとつであったスコットランドの首都エジンバラ。宗教に束縛されずに発展していたこの都市ではアイデアが自由に交わされ、北のアテネとまで呼ばれていた。エジンバラ大学、そこは大志を抱く医学生の集まるメッカ。チャールズダーウィンもその中の一人で、当時16歳であった。
すべての現象は科学的に説明できる
化石は昔の生物の残骸だ。それを調べると、生物は徐々に進化していることがわかる。絶滅した種もあった。「種」とは何だろう? それは生物の分類のひとつをいう。2匹の生き物が子供を産んで血筋を続けることができればその2匹は同じ種のものである。生物には創造主がいて、神がデザインしたと考えられていたが、すべての現象は科学的に説明できると考え、調べはじめた。
「なぜ?」から始まる
医学に興味のないダーウィンは、聖職者になってほしいという父親のすすめでケンブリッジ大学に入学する。成績は平凡だったが生物学に関しては色々と学ぶ。聖職者兼植物学者ヘンズロウ教授の植物収集の探検によくお供した。教授は、自然は見て憧れるだけでなく、「なぜ」と問い、答えを求めなければならないと教えられる。そんな彼に、運命の旅が待っていた。
ビーグル号の航海
運命を変えた手紙
ロンドン1831年、ダーウィンは22歳。運命を変える手紙が届いた。ヘンズロウがイギリス海軍ビーグル号に博物学者として乗ることを勧めたのだ。そして12月末に旅立つことになった。ダーウィンの一生を変える旅が始まったのだ。
アマゾンは生命に満ちていた
アマゾンは地球のどこよりも生物の種類が多い。撃ち落した鳥をはく製にして、標本を集めてはヘンズロウに送った。ダーウィンにとってアマゾンの毎日は冒険で、天国にいるかのようにうれしかった。ある日は虫の新種を70匹も捕まえた。アマゾンは生命に満ちていた。イグアナ、カイマン、ヤドクガエル、バク、オオアリクイ、カピバラ、オセロット、ジャガー、ピラニアなどなど。
生物が進化したのではないか
アルゼンチンでは、40体を超える化石を掘り出した。化石から昔と今の生物の間に何か関係があることを発見し、生物が進化したのではないかと考えるようになる。アンデスは地球で一番古い山脈のひとつだった。この山は地面が押し上げられてできたのかもしれない。ダーウィンは海の底から山を持ち上げる力に驚いた。
1835年、ガラパゴス。ガラパゴとはスペイン語でカメのことだ。ダーウィンがガラパゴスで見つけた生物は新種ばかりだった。そして、この遠足のような毎日が大発見につながっていくとは誰が予想できたであろう。標本はかなりの量になっていた。
ダーウィンはのちにいった ... 「ガラパゴス諸島での旅が私の全ての考えの原点であり、ビーグル号での航海が私の全生涯の道を決定した。
新しい説
進化のメカニズムを探求
1836年10月、5年ぶりのイギリス。ガラパゴスと南米は地形も気候も違うのに、生息する動物は似ていた。大陸から移住したのかもしれない。そして生物はそれぞれの島の環境に合わせて進化していったのだろうか。
生命だけが全く変わらなかったとしたら、いずれは地球の変化についていけなくなって絶滅してしまう。やっぱり生命は進化したのだろうか。ダーウィンはその「進化」の背後にある真のメカニズムを探し始めた。
マルサス『人口の原理』の影響
イギリスの経済学者トーマス・マルサスは1798年に『人口の原理(人口論)』を匿名で出版した。彼は人間の数が食料より速く増えるので、戦争、疫病、飢餓などで人口増を食い止めるしかないと言った。
英国の産業革命で大幅に人口が増え、マルサスがいたロンドンでは3人に2人は5歳までに死ぬ有様だった。食べ物には限りがあるから貧しい人をむやみに助けるべきではない、と主張したのだ。ダーウィンへの影響は大きく、それは本当にすごい結論だった。
頼もしい味方がついたダーウィン
時はたち、1839年にダーウィンはいとこのエマ・ウェッジウッドと結婚し、ロンドンの郊外に引っ越した。それからは数多くの著書をだし、植物学者のジョセフ・フッカーや動物学者のトーマス・ハクスリーなどがダーウィンの味方についた。
ダーウィンは文献を読みあさり、大勢の学者と文通し、何万もの植物や動物を飼ったりしながら実験した。
フジツボの研究で世界的権威に
10年間も没頭したフジツボの研究では世界権威になり、一人前の博物学者として認められた。ところが進化論に関しては発表するまで20年も静かにしていた。なぜそんなに時間がかかったのだろうか。
証拠のない説はただの仮定でしかない。その上、進化は人生の間で直接見られるものではないため、多くの間接的な証拠を集める必要があった。ところで、ダーウィンの研究は現在でもフジツボの学問の基盤となっている。
進化論はキリスト教を崩すことに
ダーウィンの進化論説は過激であり、出版をためらっていた。ロバート・チェンバースは生物が神に創造された後、止まることなく変化していることを化石が証拠づけていると言ったが、罰当たりだと猛烈な抗議にさらされた。神が創った完璧な動物が変わるハズがないと。進化論はキリスト教の基盤を崩し、社会をメチャメチャにしてしまうと非難された。フランス革命が起こったのもこういった自由な思想が原因だとされていた。
もうひとりのダーウィン
ダーウィンが証拠を集めている間、マレー諸島で生命の神秘の解答に近づく男がもう一人いた。アルフレッド・ラッセル・ワラスは貧しい自学の博物学者だった。熱帯の病気にかかりながらも探検を続け、進化によってできた新種を探してした。そして彼も進化が生存闘争によって生じることに気づいていたのだ。
ワラスとの共同発表
1859年7月、ロンドンのリンネ会でダーウィンとワラスの共同発表となった。ワラスは人がよく、最後までダーウィンと仲が良かった。
ダーウィンの「種の起源」は同じ年の11月24日に出版され、大ヒットし、その日のうちに1冊残らず売り切れた。しかし、その結論が気にいらない人のほうが多かった。「種の起源」は科学者にも衝撃を与え、ダーウィンの進化論は難産の説だった。なお、膨大な証拠があるにもかかわらず、進化を認めない人は今の時代でもいる。
ダーウィンの進化論
環境に順応している生命
生命は環境によく順応している。例えば、ホッキョクグマは私たちがとても住めない北極にいる。あの白い毛はガラスのように透明で光ファイバーのようにできている。この毛を通して、太陽光のエネルギーを体の方に送っていく。
また、ある種のアリは5千万年前から農業をしている。ハキリアリは巣に葉っぱを持ち帰るが、その場では食べない。持って帰った葉っぱをカビに分解してもらってから食べるのだ。カビなしではアリは餓えてしまうし、アリなしではカビも生きられない。
サケはなぜ生まれた場所に戻れるのか
イヌは人間の百万倍の嗅覚を持っている。においだけで誰だかわかってしまうほどだ。もっとすごいのはがサケで、自分が生まれたことろの味を覚えている。川の水は場所によって微妙に違う。まわりの植物や土によって、川に溶け込んでいる成分が異なっている。生れてからサケは故郷を離れ、川を下る。海に出て成熟するまで数年暮らす。その間、故郷の味は一時も忘れてはいない。広大な海から故郷の川を探し、流れをさかのぼり、まわりの水を味見しながら生まれた場所に戻る。生命は奇跡的なほどに環境によく順応して生き抜く術を備えている。
特徴の選択と変種
生物には「変種」がいる。同じ人でも見かけは多彩だ。トマトであれ色々な大きさに育つが、大きいものを選んで交配すれば、大きさを強調できる。人はこうして食物を改良してきた。種なしスイカも小さい種のスイカを選びながら栽培した。犬の種類は多いがほとんどが人間によって改良されたものだ。
旧約聖書にも人間が家畜の飼育をしていたと書いてあり、古代中国の百科事典やローマの記録にも品種改良のルールがしっかりと記述してある。
生存闘争と適者生存
人間が生物を進化させたわけではない。自然界の生物は生き残るのに精一杯だ。サケの場合、2,000個の卵のうち、1,000匹生まれ、その中から150匹が稚魚になり、大人まで育つのはわずか2匹。最後には1匹だけが故郷に戻り、子供を産む。非常にシビアな世界だ。飼育の場合は人が特徴を選択して種が進化していくが、自然界では死ぬか生きるかの「適者生存」の選択が起きる。しかし家畜の改良をする人間はたかが1万年しか存在していない。それに比べ、生命の歴史は40億年、人がいない自然ではどう特徴が選択されてきたのだろうか。
「自然淘汰」による進化論
人が飼育する時と同じく、自然界でも変種がたまに生まれた。子孫を残す前に死んでしまう弱いタイプの者は次の代に自分の特徴を遺伝できない。しかし、有利な特徴をもった変種が比較的多く子孫を残す。こうして世代ごとに特徴が変わっていき、元の種の者と子供ができなくなるくらい変わってしまったときに新しい種ができる。
つまり厳しい自然界を生き延びた変種の特徴が遺伝し、その特徴が積み重なることで進化していくのである。これが「自然淘汰」による新しい種の起源であり、進化論である。
植物の最高の智恵
自然界での試練は無数で、子孫を残す術も問われる。子孫を残すため、「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」ように何万個も産む者もいる。逆に、ほ乳類は少なく産むが子供を大事に育てる。多くの植物の花粉は風に運ばれ、受粉して種ができる。でも風だけじゃ頼りない。そこで大昔、花から蜜が出る変種があらわれた。虫が花粉を確実に運んでくれるので蜜を作る植物は繁栄した。
親指がもたらした繁栄
人間は何百万年もアフリカで進化し、そこから世界に広がって繁栄した。人間の特徴に親指がある。このおかげで器用なことができるようになった。化石から推定すると、人の祖先は400万年前に木からおり、250万年前に石で道具を作り、肉をもっと食べるようになり、脳が大幅に大きくなっていった。人間で一番特別なのは脳なのかもしれない。ネアンデルタール人のように脳が大きく、人間に似た種は他にもいたが、みな絶滅した。
人間にとって必要な精神世界
他の動物とは違い、昔から人間は死人を葬るとき墓を作って装飾品や大事な物を一緒に埋めた。美術などの芸術も自然界では類を見ない特徴だ。生き残るのに芸術は必要ないと思うが、そういうことを可能にした脳が、他の面で力を発揮している。人間は知識を後世に伝承し、遠く離れた同類に知識や情報を伝え、さらに発展し、複雑な社会も可能にした。進化は遅いから我らと6万年前の祖先とはほとんど同じだ。いまの文明が6万年前の祖先より進んでいる理由は知識の違いである。
現在でも進化論を教えない学校がある
ところで、今でも進化論を否定する人が多くいる。宗教の一部からはとくに嫌われている。人は不思議なことには神という理屈をつけがちだ。聖書は地質学と矛盾し、ダーウィンの進化論説が現れ、人々は聖書をどう解釈して良いのか迷うのだろう。現在のアメリカ合衆国でも宗教団体の圧力で、天地創造説を同等の説として学校で教えようとしているところがある。また進化論を教えていないとこもあるのだ。
ガラパゴスの生命と適者生存
生命は常に自分が生きていく時間と空間の隙間を探している。別の世界でエサを探すように進化したウミイグアナは海藻を主食にしているので食べ物には困らない。今ではイグアナの中で一番繁栄している。大昔にエサが減り、海に潜ってエサをとる者が現れた。そうして海に順応するように進化していった。海に住まいを求める進化は正解だった。ガラパゴス諸島は天然の実験室だった。
生き残ることよりも大事なこと
セミは17年の生涯のほとんどを地面の中で過ごし、土からはい出て、残りの2週間で大人になる。オスのセミは鳴いてメスを呼び、相手を求め、子供を作って死ぬ。カマキリのオスはメスと交尾した後に食われる運命にある。子供を作ることは、もしかしたら生き残ることより大事かもしれない。子供なしに死ねば、その世代でおしまいだから。
生命体の持つ本能
本能とは、生まれつき身に付いている習慣であり、不思議なものでもある。 ミツバチの集団を見てみると、女王バチ、オス、中世の働きバチがいて、仕事の分配がしっかりと決まっている。女王の役割は卵を産むことにある。オスは一切働かず、春の交尾シーズンになるまで毎日ぶらぶらしている。が、春になるとオスは互いに殺し合い、勝者だけが女王と交尾し、本望を果たしたところで死ぬ。命がけなのだ。たとえ交尾合戦を生きのびたとしても食料を消費するオスは用無しなので外に追い出され、餓え死ぬ。逆に働きバチはまじめだ。蜜を集めたり、子供や巣の面倒をみたり、女王バチにエサを与えたりし、そして巣を危険から守る。
これらの役割はみな本能によって生まれつき知っているのだ。このような本能はハチの巣全体の利益になるため、自然淘汰によって強調されていったのだろう。自然淘汰は集団でも働くということであり、本能こそ生き抜くのに不可欠なものである。
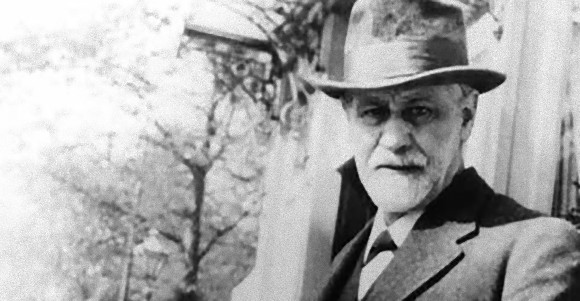
心理学者フロイトに与えた影響
ダーウィンの時代までは、人間や動物の思考や感情は説明しきれないあいまいなものとされていた。性に関係した本能を科学的に説明しようとしたダーウィンは知らずに新しい分野を開拓し、人間心理学の創始者フロイトにまで深く影響を与えた。
地理による障壁と生物の移住
自由な移動を妨げる地理的な障壁も新しい種を作る大事な要素だ。遠く離れてしまった種は別々に進化し、いずれは別の種になる。地理そのものも時間とともに変わる。巨大な氷河は地面を切り裂き地表を大きく変えてしまう。アメリカとアジア大陸が陸続きになっていた時期、マンモスやバイソンがアメリカに渡り、アジア人種も移住して北米のアメリカンインディアンや南米のインディオとなった。地理の困難を克服できる者は種にとって新しい可能性を切り開く勇者なのだ。
進化に方向性はない
大昔の世界はたった1つの細胞でできた微生物ばかりだったが、時は経ち、多細胞のものが現れ、やがて我々のような複雑な生物が現れた。確かに人間のように複雑な生命に進化するのには時間がかかる。だからといってそれが必然的な方向だとは限らない。環境に適していれば種として繁栄するし、適していなければ絶滅するまでなのだ。進化の方向は周りの環境との戦いによる。
種の絶滅
恐竜の化石はある層でいっぱいみつかるが、層が変わると一切なくなって、ほ乳類が多くなる。何か大変なことが起きて恐竜は絶滅したのだろう。このようにほとんどの種を絶滅してしまう程の出来事がここ5億年に5回くらいあった。こう化石を調べると、いつ、どの種が消えてしまったかがわかる。また天変地異などがなくても絶滅してしまった種はたくさんある。化石の記録によると、種は平均100万年で絶滅している。地球に現れた種すべてのうち、1%しか今は存在しない。
人間も種の絶滅に追いやっている
体が大きければ食べ物も多く必要になるが、恐竜は6500万年前にエベレスト山の大きさの隕石が地球に落ち、環境の変化について行けなくて絶滅したと言われている。とにかく全体から見れば絶滅は良いとも悪いとも言えない。限りある資源の中で起こる進化の必然的な要素なのだ。種が絶滅するのは自然。だが最近では人間が色々な種を絶滅に追いやっている。
エピローグ
哲学と文化に多大な影響を与えた
「種の起源」の影響はダーウィンが思ったより遥かに大きく、後戻りできないほど人類の哲学と文化に影響を及ぼした。それまで多くの人達は自分を神に特別に創られた者と考えてきたが、コペルニクスが地球は宇宙の中心ではないと言った時、人々の宇宙観が変わったように、ダーウィンの進化論は神が人に特別な立場と権利を与えたわけではないことを暗示した。ダーウィン進化論をもとにハクスリーやヘッケルは「人間は猿と共通の祖先を持つ」という研究成果を挙げ、人間は更に特別な存在ではなくなった。
全ての生き物は一つの根源に
大昔、地球を支配していた恐竜が絶滅したのも何かの激変があったためだろう。そのような偶然の出来事がなかったら、今は恐竜の世界になっていたろう。そう考えると現在人間がいるのは運命の気まぐれかもしれない。
ダーウィンは、人間とは自然の中で生き延びてきた生物達の平凡な一員で、全ての生き物は一つの根源を持つだろうと言う。
私たち生命の背後には数え切れないほどの先祖がいる。一つ一つの生涯はたとえ小さくとも、生命の壮大な物語には欠かせない一節だ。その物語は命が自然の中で磨かれてきた歴史でもある。その歴史があるからこそ、今の私たちがいる。
*『種の起源』は世界の名著です。今回の記事はほんの一部に過ぎません。ぜひこの機会に購読をおすすめします。なお、上記はマンガ「種の起源」から抜粋・要約しています。
人間の誕生、存在は「ほんの一瞬」
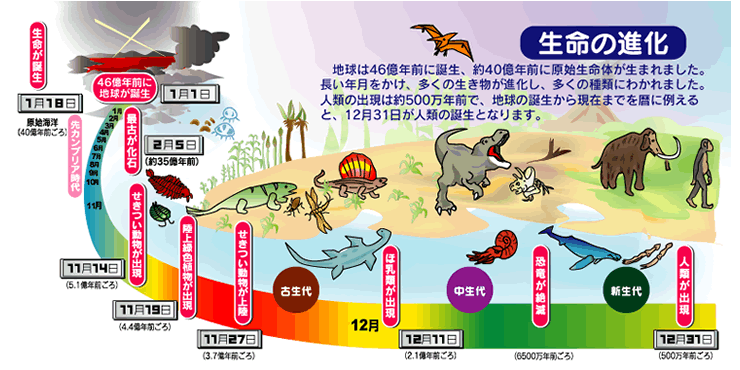
宮城県環境科学協会

人口学への招待―少子・高齢化はどこまで解明されたか (中公新書)
- 作者: 河野稠果
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2007/08/01
- メディア: 新書
- 購入: 6人 クリック: 127回
- この商品を含むブログ (39件) を見る
33-8095




